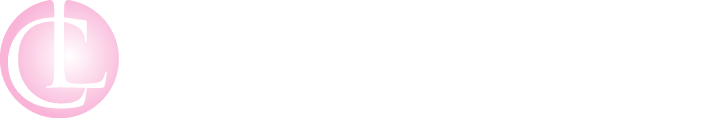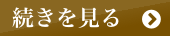定義
嫡出否認の訴えとは、嫡出子について、父子関係を否認するための裁判手続きをいいます。
解説
1 嫡出否認の訴えの対象は嫡出子(令和6年4月1日改正施行)
民法上の分類として、子は、法律上の婚姻関係にある男女間に生まれた子(嫡出子といいます)と、そうでない子(非嫡出子といいます)に、分類されています。
嫡出否認の訴えは、嫡出子についての親子関係を争う裁判手続きです。
妻から婚姻中に生まれた子は一律に夫の子(嫡出子)と推定されます。また、離婚後300日以内に生まれた子は、原則として、元夫の子と推定されますが、例外的に、その出生の時までに母が再婚した場合は、再婚後の夫の子と推定されます。(民法772条。詳しくは、嫡出子の解説を参照ください)。
嫡出子との親子関係を争いたい場合、嫡出否認の訴えによるほかありません。
なお、民法772条の嫡出推定の規定は、令和6年4月1日に改正施行されました。改正前の規定は、「婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」と定められていました。そのため、離婚等の日から300日以内に元夫以外の者との間の子を出産した女性が、その子が元夫の子と扱われることを避けるために出生届の提出をためらい、結果として無戸籍者が多数存在するという社会問題が生じていました。そこで、改正後の規定では、離婚後300日以内に子が出生した場合でも、出生の時までに母が再婚した場合は、再婚後の夫の子と推定されることになりました。
2 嫡出否認の訴えの提訴権者
嫡出否認の訴えを提起できるのは、①父と推定される(元)夫、②子(親権を行う母、親権を行う養親、未成年後見人は、子のために(子を代理して)訴訟提起可)、③母(ただし、母による否認権の行使が子の利益を害することが明らかなときを除く。)、④(再婚後の夫の子と推定される子に関し)母の再婚前の夫(ただし、再婚前の夫による否認権の行使が子の利益を害することが明らかなときを除く。)です。
なお、改正前の規定では、嫡出否認の訴えを提訴できるのは、①父と推定される(元)夫に限られており、母や子から嫡出否認の訴えを提起することはできませんでした。
3 嫡出否認の出訴期間
嫡出否認の訴えの出訴期間は下表のとおりです。
| 申立人 | 相手方 | 原則的出訴期間 |
| 父と推定される(元)夫 | 子又は親権を行う母 | (元)夫が子の出生を知った時から3年以内 |
| 子※1※2 (親権を行う母、親権を行う養親、未成年後見人は、子のために(子を代理して)申立て可) | (元)夫 | 子の出生の時から3年以内※3 |
| 母※1※2 (ただし、母による否認権の行使が子の利益を害することが明らかなときを除く) | (元)夫 | 子の出生の時から3年以内 |
| (再婚後の夫の子と推定される子に関し)母の再婚前の夫※1 (ただし、再婚前の夫による否認権の行使が子の利益を害することが明らかなときを除く) | 再婚後の夫及び子又は親権を行う母 | 母の再婚前の夫が子の出生を知った時から3年以内 |
※1 令和6年4月1日以降に出生した子について訴訟提起できます。
※2 経過措置として、令和6年4月1日から1年間に限り、令和6年4月1日より前に出生した子についても、子又は母が訴訟提起できます。
※3 子は、(元)夫と継続して同居した期間が3年を下回る等の要件を満たすときには、21歳に達するまで(出生の時から3年が経過した後も)、訴訟提起できます。ただし、親権を行う母等が子のために(子を代理して)訴訟提起する場合には、この限りではなく、上記の原則的出訴期間(子の出生の時から3年以内)に限って訴訟提起できます。
なお、改正前の規定では、父と推定される(元)夫が、子の出生を知った時から1年以内に提起しなければなりませんでした。
4 嫡出否認の手続き・流れ
嫡出否認の訴えは、調停前置主義の適用があります(家事事件手続法257条、同244条、人事訴訟法2条2号)。
したがって、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に、嫡出否認調停を申し立てます。
当事者で管轄の合意がある場合は、合意した家庭裁判所に申し立てることもできます。
嫡出否認調停において、当事者間で、夫の子でないという合意ができた場合、家庭裁判所が必要な調査を行った上で、その合意が正当であると認められれば、合意に従った審判がなされます。
合意ができなかった場合、嫡出否認訴訟を提起し、父子関係を争うことになります。
なお、嫡出子であっても、夫が長期の海外出張、受刑、別居等で子の母と性的交渉がなかった場合など、妻が夫の子を妊娠する可能性がないことが客観的に明白である場合には、夫の子であるとの推定は及びません。このような場合には、親子関係不存在確認の訴えで、親子関係を争うことができます。
関連用語
関連条文
民法772条(嫡出の推定)
1項 妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。
2項 前項の場合において、婚姻の成立の日から二百日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定し、婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
3項 第一項の場合において、女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に二以上の婚姻をしていたときは、その子は、その出生の直近の婚姻における夫の子と推定する。
4項 前三項の規定により父が定められた子について、第七百七十四条の規定によりその父の嫡出であることが否認された場合における前項の規定の適用については、同項中「直近の婚姻」とあるのは、「直近の婚姻(第七百七十四条の規定により子がその嫡出であることが否認された夫との間の婚姻を除く。)」とする。
同774条(嫡出の否認)
1項 第七百七十二条の規定により子の父が定められる場合において、父又は子は、子が嫡出であることを否認することができる。
2項 前項の規定による子の否認権は、親権を行う母、親権を行う養親又は未成年後見人が、子のために行使することができる。
3項 第一項に規定する場合において、母は、子が嫡出であることを否認することができる。ただし、その否認権の行使が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。
4項 第七百七十二条第三項の規定により子の父が定められる場合において、子の懐胎の時から出生の時までの間に母と婚姻していた者であって、子の父以外のもの(以下「前夫」という。)は、子が嫡出であることを否認することができる。ただし、その否認権の行使が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。
5項 前項の規定による否認権を行使し、第七百七十二条第四項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により新たに子の父と定められた者は、第一項の規定にかかわらず、子が自らの嫡出であることを否認することができない。
同775条(嫡出否認の訴え)
1項 次の各号に掲げる否認権は、それぞれ当該各号に定める者に対する嫡出否認の訴えによって行う。
一 父の否認権 子又は親権を行う母
二 子の否認権 父
三 母の否認権 父
四 前夫の否認権 父及び子又は親権を行う母
2項 前項第一号又は第四号に掲げる否認権を親権を行う母に対し行使しようとする場合において、親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。
同776条(嫡出の承認)
父又は母は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、それぞれその否認権を失う。
同777条(嫡出否認の訴えの出訴期間)
次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、それぞれ当該各号に定める時から三年以内に提起しなければならない。
一 父の否認権 父が子の出生を知った時
二 子の否認権 その出生の時
三 母の否認権 子の出生の時
四 前夫の否認権 前夫が子の出生を知った時
同778条
第七百七十二条第三項の規定により父が定められた子について第七百七十四条の規定により嫡出であることが否認されたときは、次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、前条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める時から一年以内に提起しなければならない。
一 第七百七十二条第四項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により新たに子の父と定められた者の否認権 新たに子の父と定められた者が当該子に係る嫡出否認の裁判が確定したことを知った時
二 子の否認権 子が前号の裁判が確定したことを知った時
三 母の否認権 母が第一号の裁判が確定したことを知った時
四 前夫の否認権 前夫が第一号の裁判が確定したことを知った時
家事事件手続法244条
家庭裁判所は、人事に関する訴訟事件その他家庭に関する事件(別表第一に掲げる事項についての事件を除く。)について調停を行うほか、この編の定めるところにより審判をする。
同257条
第二百四十四条の規定により調停を行うことができる事件について訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に家事調停の申立てをしなければならない。
人事訴訟法2条
この法律において「人事訴訟」とは、次に掲げる訴えその他の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする訴え(以下「人事に関する訴え」という。)に係る訴訟をいう。
1号 (略)
2号 嫡出否認の訴え、認知の訴え、認知の無効及び取消しの訴え、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百七十三条の規定により父を定めることを目的とする訴え並びに実親子関係の存否の確認の訴え
3号 (略)